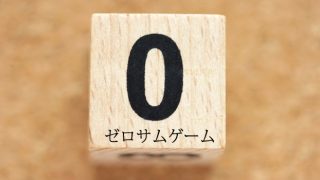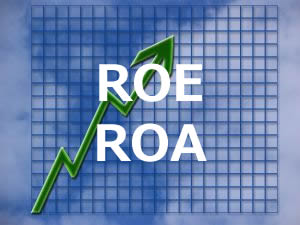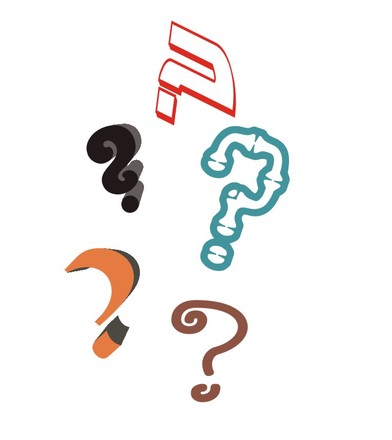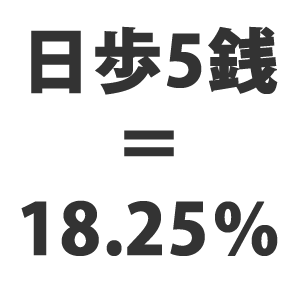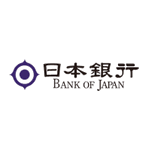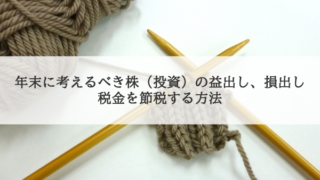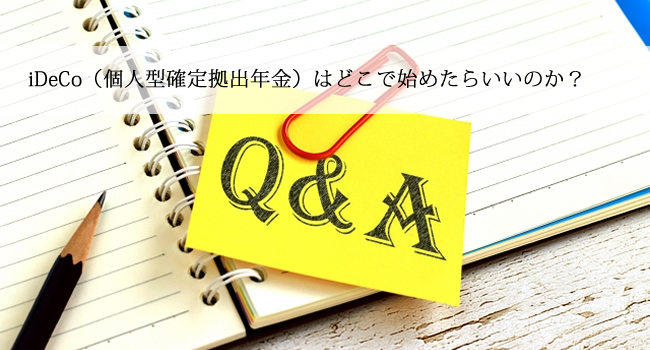
税制上の優遇が大きなiDeCo(個人型確定拠出年金)の利用者が急増しています。老後に向けての資産形成において現状では最強ともいえる制度です。
・掛け金全額税額控除(納付しやすい)
・運用益は非課税(複利効果の大幅UP)
ということで、老後(60歳以降)に使う予定のお金であれば基本的にはiDeCoとして運用しましょう。そんなiDeCoを初めて使うときに気になるのが「どこでiDeCoを始めたらいいのか?」ということではないでしょうか。
iDeCoはどこで始めてもいいわけじゃあありません。大切なのは「手数料」と「取扱商品」です。今回はそんなiDeCoの具体的な始め方と銀行、証券会社を徹底比較します。
iDeCoを始めるまでの流れ
なお、iDeCoってそもそも何?という人は先に以下の記事を読んでおくことをお勧めします。

iDeCo(個人型確定拠出年金)を初めてスタートするにあたっては以下の手続きの流れが必要になります。
- どこで積み立てをするのかの金融機関を選ぶ
- 必要書類などを準備する
- 口座開設をする
- 積み立てる金額と運用する商品を決める(後から変更可能)
ちなみん、金融機関については後から「移管」という手続きをとれば変更することはできますので、今現在で一番自分に合ってる金融機関を選んでおけば問題ないです。
iDeCoを始めるにあたっての必要書類
- 本人確認書類(免許証など)
- 年金番号がわかるもの(年金手帳など)
が必要になります。基礎年金番号は年金手帳にかかれているほか、「ねんきん定期便」や「ねんきん特別便」などにも記載されています。
ねんきん定期便は捨てたし、年金手帳は会社に預けているという方は、会社に確認してもらいましょう。別に理由を聞かれることはないはずです。
iDeCoにおける金融機関選びのポイント
今給与振込とかにつかっている銀行でもiDeCoやってるみたいだし、そこでいいか。
と思っているのであればご注意です。iDeCoを利用するにあたっては金融機関選びもかなり重要な要素となっています。理由は手数料と商品です。
iDeCo関連の手数料は金融機関でも大きく違う
まずは、iDeCoの手数料ですね。これは金融機関によって大きく違っています。iDeCoを運用するにあたっては以下の手数料が毎月かかります。
- 国民年金基金連合会手数料:103円(固定)
- 事務委託金融機関手数料:64円(固定)
- 運営管理機関手数料:0円~400円くらい(金融機関で異なる)
重要なところは赤でマーカーひいときました。そうです。運営管理機関手数料って銀行、証券会社などで幅があるんです。無料から毎月400円くらいで設定されています。
手数料が高い金融機関だと年間に5000円ほどですよ。iDeCoは60歳まで加入するとして仮に30年だとしたら15万円も余分に手数料を払うことになるんです。
実に勿体ない話ですよね。
取扱商品も金融機関で異なる
iDeCoで取り扱っている金融商品(主に運用商品は投資信託)も金融機関で異なります。
この投資信託も低コストなタイプをちゃんとラインナップしているところもあれば、言い方はお下品ですがクソみたいな高コストファンドを“あえて”提供しているところもあります。
たとえば、代表的な運用商品である日経225(日経平均)に連動する投資信託をみてみます。
楽天証券やSBI証券などのネット証券の場合、信託報酬0.2%程度のファンドを扱っています。一方で、某地方銀行では同じ日経平均連動ファンドを扱っていて、手数料は0.7%です……。
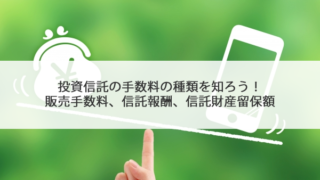
信託報酬は投資信託の運用コストです、このコストは運用利回りに悪影響しかありません。同じ運用スタイルならコストが安いものの方が絶対にお勧めです。
なお、なぜ手数料が高いファンドを売るのか?っていうと、販売者(金融機関)はこの信託報酬の半分くらいをもらえる契約になっているからです。
手数料がバカ高いファンドを売っている銀行は、もっといい商品があるのに、明らかに割高なボッタクリ商品を売りつけているわけです。個人的にはそんな金融機関とはお取引したくないですね……。
僕は別に、銀行や証券会社はユーザーに対して無償奉仕しろなんて思っていません。でも、明らかにユーザーにとって有利な商品があるのに、それを無視して自社が一番儲かる商品しか置かないっては、お金を扱う金融機関としてはどうかと思います。
いわゆる「フィデューシャリー・デューティー」という責任を果たしていません。
でも、ネット系よりは安心できる規模の大きなところが……
iDeCo(個人型確定拠出年金)の財産は利用している証券会社や銀行などの金融機関が直接預かっているわけではありません。
万が一、iDeCoを利用している証券会社や銀行が破綻した場合でも利用者の財産は確実に保護される仕組みができているので安心してください。
余談ですが、個人的にはむしろ会社の将来(健全性)でいえば地銀とかの方がヤバイ気がしてます。
iDeCo運用にお勧めの金融機関
じゃあ、具体的にiDeCoを始めるにあたっておすすめの金融機関を比較していきます。いかにあげる金融機関であれば、コスト的にも扱っている商品的にも全く問題ございません。
これらの中から選ぶべきです(ちなみに、iDeCo口座として運用できるのは一人一つまでです)。ちなみに、どの証券会社も無条件で運営管理機関手数料が無料となっています。
- SBI証券(取扱商品が多め。積極投資したい人向け)
- マネックス証券(低コストファンドが多く、シンプル)
- 楽天証券(バランスファンドが充実)
いずれも大手のネット証券ですね。もう少し各社のサービスを以下で紹介したいと思います。
SBI証券 iDeCoの提供サービスでは一日の長

取扱ファンド数も多く、いずれもローコストファンドが多いです。
iDeCoをこれから始めたいという方にとってはSBI証券を選択しておいて間違いだと思うことはないでしょう。特に、投資に慣れた方にとっては一押しです。
マネックス証券 シンプル設計で最安値のファンドが多い

他の証券会社が高いというわけではないのですが0.001%の単位でも安いファンドをそろえているところに好感が持てます。セミナー等も充実しているので初心者の方にお勧め。
楽天証券 バランスファンドが多い、投資に興味がない人に

取扱ファンドはSBI証券、マネックス証券と似たり寄ったりですが、「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」のような、これ一本買っておけば世界に分散投資できるようなバランス型ファンドがあるのが強みです。
投資とか考えたくない方でも、これに投資しておけばある意味、分散投資が完了するというものです。
少なくとも、iDeCoは、収入がある20歳以上の方であれば、始めない理由がないほど、お得な制度となっています。
先延ばしするよりも早めに手続きをしてしまったほうが絶対にお得です。せっかくの税制優遇措置なので上手に活用しましょう。