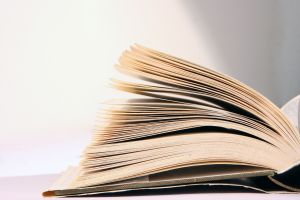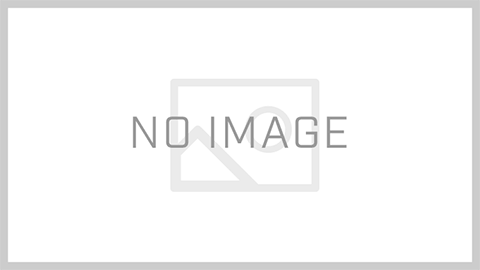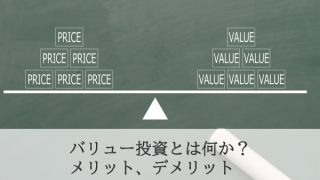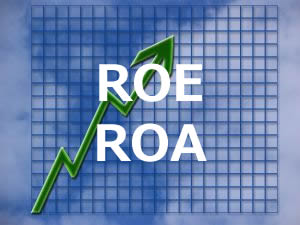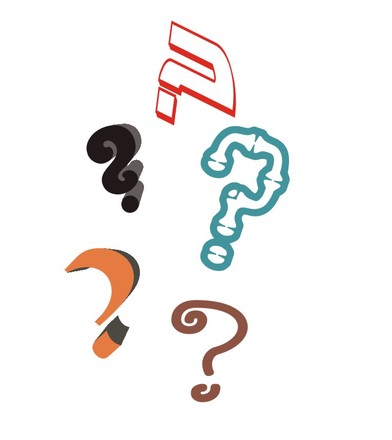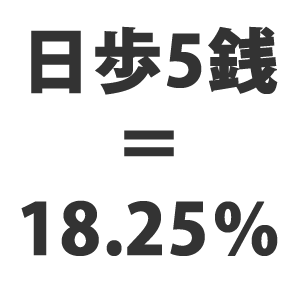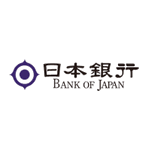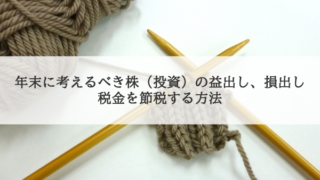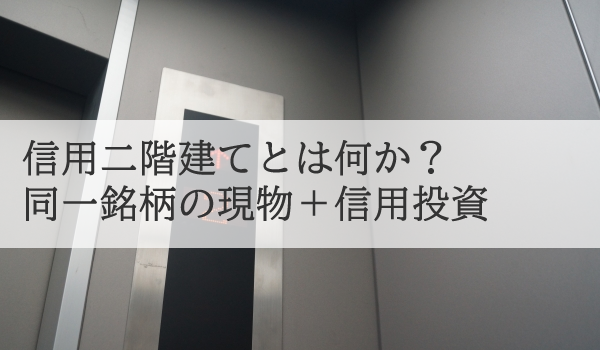
信用取引は、保有している現金(預り金)や現物株式(代用有価証券)を担保として株の売買を行うことができます。その信用取引において“二階建て”という言葉が使われることがあります。
これは、ある株の現物株を持った状態で同一銘柄を信用取引でも買うという状態です。
100万円分の現物A社株を担保(80%の80万円相当)を担保にその担保をもとにA社株を信用取引で買うといった形ですね。
この信用二階建ては変動によるリスクが増幅され、追証や強制ロスカットなどが発生しやすくなります。特にご注意ください。
信用取引の担保(代用有価証券)について
まず、信用取引をするには担保として「証拠金」を証券会社に預ける必要があります。といっても、特別なものではなく、証券会社に入金している預かり金は自動的に証拠金となります。
また、この現金以外にも「代用有価証券」というものが証拠金として担保になります。代用有価証券とは以下のようなものが挙げられます。
- 国債/地方債/社債等の債券
- 現物株式(上場企業)
- 投資信託(公社債投資信託/株式投資信託)
いずれも時価が証拠金となりますが、時価に対して「代用掛目」という補正値を掛けて計算します。たとえば、日本国債は95%、現物株式は80%といった具合です。
つまり、現物株として100万円分を預けていれば、その80%の80万円の証拠金として扱ってくれるわけです。
株を担保に株を買う、信用二階建て
さて、表題の信用二階建てに話を戻しますと、これは株を担保に株を買うことを二階建てといいます。
一般的には担保に入れている株と同一の銘柄を信用取引で買うことを指します。二階建てを利用することでレバレッジの度合いが高まり、運用はより効率的になりますが、リスクも増大します。
二階建ては上手くいくときは上手くいく
信用二階建てはレバレッジの強化手段になります。
たとえば、A社株を1000円×1000株分保有しているとして、これを代用有価証券として担保に入れている状態だとします。100万円分で代用掛目80%として80万円になりますね。
そして、その状態でA社株を信用取引で1000円×2500株購入したとします。250万円分ですね。
保有株数は3500株となり、10%の上昇で得られる利益は35万円です。運用資金は100万円なので元本比では35%の利益となり、これは3.5倍のレバレッジ取引となります。
投資が思惑通りに動く場合はこれでいいです。少ない資金でも効率的に投資できるわけですからね。ただ、問題はマイナス方向に動いた時です。
信用二階建ての株価下落と維持率低下

レバレッジ取引は効率的に運用できる半面で、マイナスも加速させることになりますので、運用には注意が必要です。
さらに、信用取引の場合、信用二階建てを利用すると、株価下落によって「元本毀損で証拠金マイナス」と「信用取引の含み損」がダブルで影響するため、証拠金維持率がモリモリ下がってしまうという構造的問題があります。
当初維持率
前述のケースで維持率を計算してみましょう。
証拠金:80万円(1000円×1000株×80%)
買建:250万円
維持率:32%(80/250)
これがA社株の下落でどのような形で維持率が下がるかを計算します。
株価下落と維持率の変化
で、実際に子の状態でA社株が下落していくと維持率がどう変化していくか?ということをまとめたのが以下です。
| A社株価 | 担保価値 | 信用含み損 | 実質証拠金 | 信用維持率 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 800000 | 0 | 800000 | 32.00% |
| 990 | 792000 | -25000 | 767000 | 30.68% |
| 980 | 784000 | -50000 | 734000 | 29.36% |
| 970 | 776000 | -75000 | 701000 | 28.04% |
| 960 | 768000 | -100000 | 668000 | 26.72% |
| 950 | 760000 | -125000 | 635000 | 25.40% |
| 940 | 752000 | -150000 | 602000 | 24.08% |
| 930 | 744000 | -175000 | 569000 | 22.76% |
| 920 | 736000 | -200000 | 536000 | 21.44% |
| 910 | 728000 | -225000 | 503000 | 20.12% |
| 900 | 720000 | -250000 | 470000 | 18.80% |
| 890 | 712000 | -275000 | 437000 | 17.48% |
| 880 | 704000 | -300000 | 404000 | 16.16% |
| 870 | 696000 | -325000 | 371000 | 14.84% |
| 860 | 688000 | -350000 | 338000 | 13.52% |
| 850 | 680000 | -375000 | 305000 | 12.20% |
| 840 | 672000 | -400000 | 272000 | 10.88% |
| 830 | 664000 | -425000 | 239000 | 9.56% |
| 820 | 656000 | -450000 | 206000 | 8.24% |
| 810 | 648000 | -475000 | 173000 | 6.92% |
| 800 | 640000 | -500000 | 140000 | 5.60% |
| 790 | 632000 | -525000 | 107000 | 4.28% |
| 780 | 624000 | -550000 | 74000 | 2.96% |
| 770 | 616000 | -575000 | 41000 | 1.64% |
| 760 | 608000 | -600000 | 8000 | 0.32% |
| 750 | 600000 | -625000 | -25000 | -1.00% |
投資時点から10%下落した900円時点(背景ピンク)のところで、追証が発生するラインとなります。
信用二階建ての状態だと、信用建玉の含み損分だけでなく株価下落によって担保価値も減少してしまいます。もしも、二階建てにせず、現金のまま証拠金としていれば、追証が発生するのは800円(20%下落)を下回ったタイミングとなります。
強烈な下落だと借金を背負う結果にも
仮に、強烈なマイナス材料がでて、ストップ安が続くような場合、信用二階建ては資産全部を失うだけでなく、マイナス(借金)が残る可能性も出てきます。
ストップ安張り付きとなって株が売れず、どんどん値下がりして結局借金が残ってしまった……という事になるかもしれません。
株の場合、二階建てでも3.5倍程度のレバレッジなので100%を失うには30%弱の値下がりが必要になりますが、強烈なマイナス材料の場合、なきmにしにもあらずです。
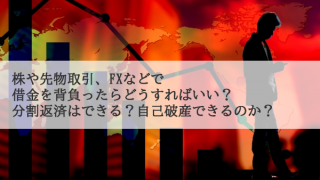
「卵は一つの籠に盛るな」という相場格言もあります。信用取引をするのであれば、一銘柄の失敗で全財産失うなんてことにならないように一定のリスク分散を心がけましょう。