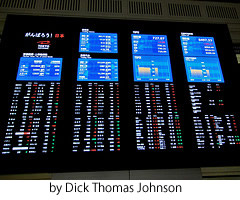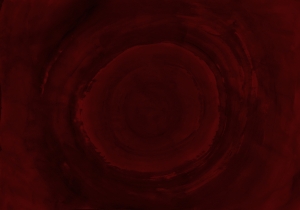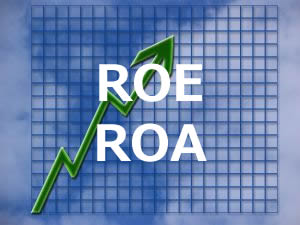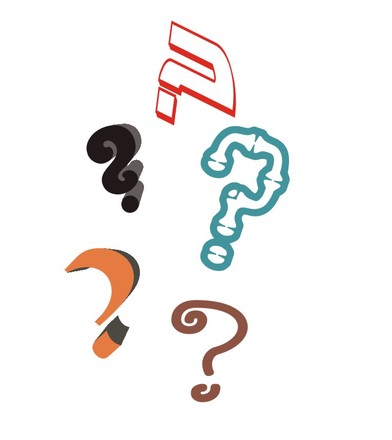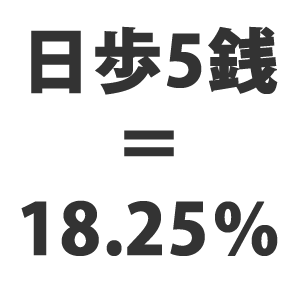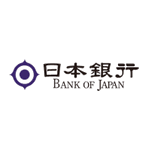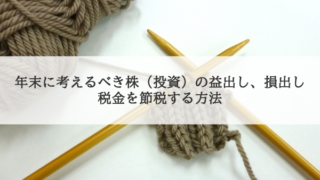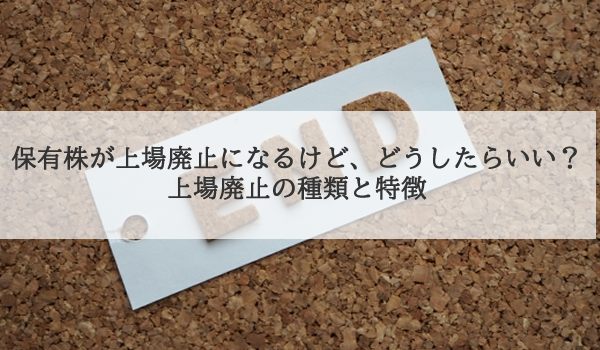
上場廃止というのは、証券取引所で売買されている株式が売買できなくなることを指します。
基本的にはネガティブ(マイナス)材料となりますが、上場廃止は必ずしも倒産を意味するわけではありません。上場廃止となるのは様々な理由があります。
今回は上場廃止となるケース別に、投資家はどのように判断するべきでどう行動するべきなのかを紹介していきます。
もくじ
上場廃止とはどういう意味なのか?
上場廃止というのは証券取引所(東京証券取引所など)で取引されている株式が以降取引できなくなることです。証券取引所には“上場廃止基準”というルールがあり、それに抵触してしまうと上場廃止となります。
この上場廃止となる理由は以下が挙げられます(東証1部・2部)。
- 株主数が400人を下回る
- 流通株が2000単位未満
- 流通株時価総額が5億円未満
- 流通株比率が5%未満
- 時間総額が一定を下回る
- 債務超過となった
- 証券取引所での売買高が一定を下回る
- 有価証券報告書等の提出遅延
- 虚偽記載、不適正意見等があった
- 特設注意市場銘柄に該当、指定されているが改善の見込みがない
- 上場契約に違反した
こんな感じです。結構いろいろありますよね。「債務超過(負債を資産が上回る)」というような財務的な要件もありますが、流通株(市場で取引される株)が著しく減少するなどして上場企業にふさわしくないケースでも上場廃止となります。
上場廃止には大きく3つのパターンがある
上場廃止には、色々な理由がありますが大きく分類すると3つに分けられます。
- 倒産・破綻するケース
- 不祥事などによって上場廃止となるケース
- TOB(買収・MBO)などによって上場廃止となるケース
どれに該当するかで上場廃止が決まった後の株価の動きも当然違ってきます。
倒産・破綻するケース
会社の業績が悪化するなどして、倒産が濃厚であるケースです。このケースが一番投資家にとってはダメージが大きいといえるでしょう。
基本的に、上場廃止後には会社がなくなってしまいますので、株の価値はほぼゼロになります。株主には会社清算後に「残余財産の分配を受ける権利」がありますが、債務超過となっているような会社の場合にはそれも期待できません。
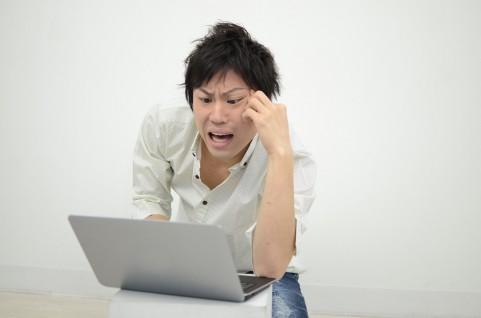
必ずしも倒産して会社が消滅するケースでなくても、JAL(日本航空)のケースのように100%減資+第三者割当増資のような形で、既存投資家には何も残らないことが多いです。
不祥事や上場廃止基準抵触によって上場廃止となるケース
前述のように上場廃止基準には色々な基準があります。この基準を満たせずに(ルール違反をして)上場廃止となることがあります。
一般的に、ルール違反=即上場廃止というわけではありませんが、繰り返したケースが違反が悪質な場合は上場廃止となります。
倒産の場合と違い、会社が存続するケースも多く、株式としての価値は残ります。一例としては西武鉄道などが挙げられますね。2005年に上場廃止となりましたが、2014年に西武ホールディングスとして再上場しています。
ただし、上場廃止となった場合、自由に株を売買することはできなくなりますので、現金化などは困難となります。
TOB(買収・MBO)などによって上場廃止となるケース
今回紹介する上場廃止の中では比較的ポジティブなケースです。
TOB=株式公開買い付けといって、価格と数量を公示して株を買付することを指します。
TOB=上場廃止ではありませんが、TOBによってその会社を子会社化して上場廃止にするというようなケースもあります。
TOBに応募することでそれに対応してもよいですし、売却に応じないこともできます。ただし、TOBによって完全子会社化される場合、株式交換によってその会社の株が交換された株になることもあります。
経営陣がMBO(マネジメントバイアウト)という形で自ら株をTOBにより買い取り、上場廃止を選択することがあります。
上場廃止までの流れ
上場廃止基準に当てはまる可能性がある銘柄は「監理銘柄(監理ポスト)」に指定されます。この段階では株取引は可能ですし、その後、監理銘柄の指定が外されるケースもあります。
一方で、上場廃止が決まると「整理銘柄(整理ポスト)」に指定されます。その後1か月は取引できますが、その後上場廃止となります。
上場廃止決定後はマネーゲームになることもある
倒産のような超ネガティブな理由で上場廃止となるような場合、ストップ安が連続して続きた後、意外な値段で寄り付く(売買成立)となることがあります。
これは単純なマネーゲームであり、売り買いが交錯し、乱高下することがあります。倒産株の場合、上場廃止に近づくにつれて1円に近づいていきますが、短期的な値動きを狙った売買が行われることがあります。