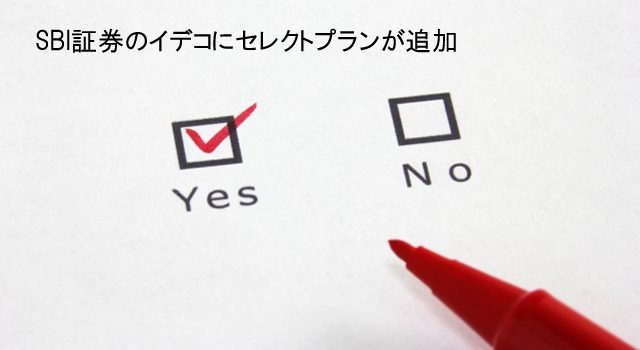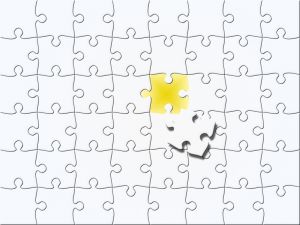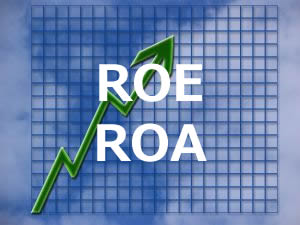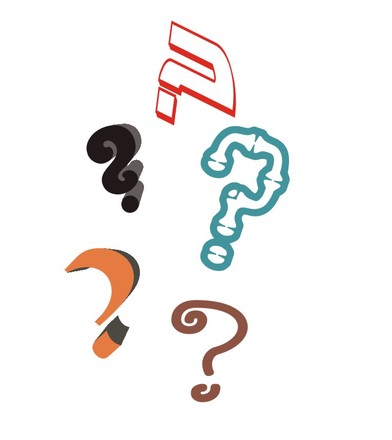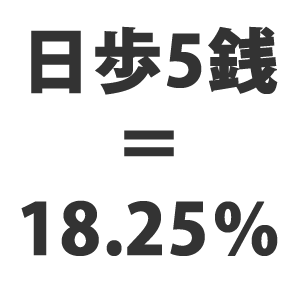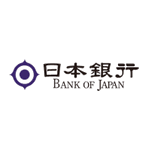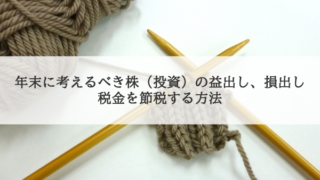自分で保険の知識を身につけることは重要
生命保険などの保険への加入を保険レディ(営業マン)や保険ショップなどの勧めるがままに加入していると言う人も少なくないと聞きます。
でも、保険料は長期にわたって支払うことになるため、人生トータルではかなりの金額を費やすことになります。人生の三大出費と呼ばれることもありますね。
そんな大きな買い物である保険。ご存じの方も多いかと思いますが、「金融商品としてはかなり割が悪い」商品です。入らないで良いなら入らない方が経済的には得をします。
だからこそ、勧められるがままの保険に入るのではなく、必要最小限の保険に入ると言うことが極めて重要です。そのためには、加入者自身が知識を身につけるというのがとっても重要なことなのです。
今回の「定期保険と終身保険と養老保険の特徴とそれぞれの違い」の記事ではそうした自分で保険を考えたいという方にとって基本となる記事です。
定期保険
定期保険とは、「掛け捨て」型の保険です。保険料を払っている間だけ保険が効き、満期になったら(解約したら)それでおしまいという保険になります。
掛け捨ては損というイメージを持たれるかもしれませんが、その分、保険料は割安です。少ない保険料である程度の保障を求めるのであれば定期保険が適切と言えます。
一方で運用性はほぼ皆無ですので、万が一に備えるためだけの保険といえます。
主に「死亡」に備える保険となります。
世帯主などが自分が死亡した時などの死亡保障として適した保険といえるでしょう。
終身保険
一生涯の保障があるのが終身保険です。満期はなく、何歳でも死亡したら保険金が支払われます。また途中で解約した場合でも「解約返戻金」という形でまとまったお金が戻ってきます。加入期間や予定利率などによっても変わりますが、払いこんだ保険料以上の返戻金となるケースもあります。
ただし、加入期間が短い場合などは返戻金も小さくなります。貯蓄性があるため有利に見えますが、その分がプラスされた保険料が発生することになるので保険料は定期保険と比べて高額となります。
加入年数が長くならないと貯蓄性も期待できないので、超長期の老後資金などを含めた形での検討が重要です。
養老保険
こちらはより貯蓄性の高い保険です。満期が設定されており、途中で死亡すれば「死亡保険金」が出て、満期まで生存していた場合には「満期保険金」を受け取ることができます。
満期時にまとまったお金が戻ってくることになるので目的を決めて貯金と考えるのもありです。途中で解約した場合でも返戻金という形で一定のお金が戻ってきます。
ただし、終身保険と同じように短期で解約した場合はほとんど戻ってきません。また、保険料も定期保険と比べるとかなり高額になります。
何に備えるかで選択するべき保険は変わる。また、保険だけで検討する必要もない
保険を選択する場合、何に備えたいのかという目的で選ぶべき保険は変わります。
また、すべてを保険だけで考える必要は全くありません。
たとえば、死亡保障については定期保険でカバーしておいて、貯蓄機能は「定期預金」や「積立預金」などでも十分に対応できます。
運用性を考えるのであれば、投資信託や株式投資のような運用商品だって沢山あります。
この保険に入れば死亡保障も運用も同時にカバーできます。という保険は便利なように見えますが、ライフスタイルの変化や収入の変化などによる細かな調整には向きません。
保障は保障、貯蓄は貯蓄、運用は運用とそれぞれの目的に応じてシンプルに運用する方が見直しも変更も容易にできます。個人的にはシンプルな保険設計をお勧めします。
また、冒頭にも書きましたが、保険は基本的に有利な商品では決してありません。
「生命保険・医療保険は「損」をする金融商品」などでも書かれている通り、どちらかといえば割の悪い金融商品です。
各保険会社は数字を公表しませんが、支払っている保険料に占める事業費率(付加保険料)は20%を超えるものはザラです。つまり、払っている保険料の20%以上は保険会社の儲けや経費に消えているわけです(保険によっては50%近いものもあります)。
付加保険料が安めのネット生保なども登場してきてはいるものの、やはり保険の難しさからか加入者あまり増えていないようです。理由は保険の難しさなどもあるのでしょう。
とにかく、現在のところ生命保険による手数料が競争などもあまり起こっていません。
そのため、賢く保険を使うには「コストの高い保険は必要最小限しか入らない」というのが有効的だと言えるでしょう。